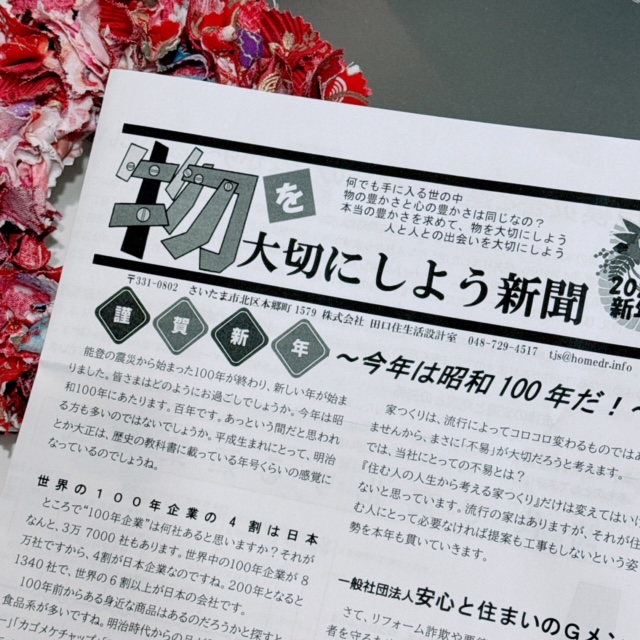2025.02.17
中古住宅購入時の注意点を建築士が解説
中古住宅は新築に比べ、価格面で魅力がある一方で、注意すべき点も多く存在します。後悔しないマイホーム購入のためには、購入前にどのような点を意識すれば良いのでしょうか?
本記事では建築士の視点から、中古住宅購入時の注意点を「建物の状態」「土地と周辺環境」「契約」の3つの観点から解説します。 具体的なチェックポイントを参考に、理想の住まい探しを実現しましょう。
住宅診断(ホームインスペクション)とは、専門家である住宅診断士が、第三者的な立場から住宅の状態を診断することです。この診断を受けると、建物の構造耐力上の安全性や劣化状況など、中古住宅のおおまかな情報を知ることができます。
ただし、インスペクションは目に見える劣化だけを見つける作業で、床下や屋根裏を詳細に調査することはしませんし、劣化の原因が何かを追究することもないので、出来れば耐震診断をおすすめします。
中古住宅を選ぶ際は、以下の項目をチェックしておきましょう。
【耐震性を確認する】
中古住宅の耐震性は、建物の状態を判断する上で重要な要素です。とくに耐震性については、どの建築基準法の時代に建てられたかを確認することが大切です。2000年6月以降に建築確認申請された物件であれば、改正後の耐震基準で建てられているため、比較的安心だといえます。
それ以前に建設された建物の場合は、耐震診断を行うか、耐震補強工事済みの物件を選ぶことをおすすめします。
建築時の確認申請書類が残っている場合は、そちらを確認しましょう。「耐震基準適合証明書」や「住宅性能評価書」などの書類は、耐震基準を守って建設された証しです。
【建物の劣化状況を見る】
安心して中古住宅を購入するために、建物の劣化状況を確認しておくことが大切です。前述の住宅診断をおこなうことによって、欠陥中古住宅を購入するリスクを抑えることができます。また、目視で確認できる壁や床などは、細部まで状態をチェックしましょう。
【屋根の劣化状況を確認する】
屋根の劣化も、家全体の安全性と快適性に影響を与えます。屋根を上から見ることは現実的に難しいですが、もし目視できる範囲で劣化が見られた場合には、専門家による詳細な診断をおこないましょう。
下屋根を見れる場合は、ある程度の劣化状況が分かるので確認することをおすすめします。カビやコケが発生していないか、屋根の下地が見えていないかなど、セルフチェックしてみてください。
【電気設備のチェック】
中古住宅選びの際は、電気設備のチェックも怠らないようにしましょう。室内にある分電盤を見るとA(アンペア)の値が分かります。もし、アンペア数が不足していたり、何らかの不具合が見られる場合は、修繕費がかかることを想定しておきましょう。
中古住宅を購入する際は、建物そのものだけでなく、周辺環境の確認も欠かせません。とくに以下の点に留意して住宅を選ぶとよいでしょう。
【災害リスクの確認】
中古住宅の購入時には災害リスクを考慮することが大切です。建物自体が良い物件だったとしても、浸水しやすいエリアだったり、地盤が弱いエリアだったりする可能性があります。そのため、ハザードマップを確認しておくことが大切です。
ハザードマップとは、該当地域にどのような災害のリスクがあるのかを地図に示したもので、地震・洪水・津波・高潮・土砂災害などのリスクが示されています。多くの自治体がハザードマップを作成しており、インターネット上でも確認できるので、ご自身でも検索してみてください。
【立地環境をチェック】
市場価格よりも明らかに安価な物件を見つけた場合、いくらお買い得だと感じても、注意が必要です。
安いのには何かしらの理由がある場合がほとんどでしょう。
例えば、公道に面している幅が2mより少ないと再建築不可物件となり、さまざまな工事に影響が出ます。次に売却する際も、なかなか売れないといったリスクがあります。そのほかには、土地に問題があったり(地盤が弱い、境界線トラブルがあるなど)、心理的瑕疵などの可能性もあります。
中古住宅の購入は、新築に比べて価格が安く選択肢も多い反面、さまざまな点に注意が必要です。本記事で紹介したチェックポイントを参考に、物件選びを進めてください。
住宅診断の活用や、専門家への相談などを利用することで、中古住宅のリスクは軽減されます。適切な対策と情報収集をおこなうことで、後悔のない中古住宅購入を実現できるでしょう。
中古住宅の状態や耐震強度を知りたい方には、田口住生活設計室の「耐震診断」がおすすめです。床下に自ら潜って、しっかりと調査いたします。耐震診断の実績は累計1,000件以上。耐震診断なら、さいたま市の田口住生活設計室にお任せください。
耐震診断の詳細はこちらから>>>
本記事では建築士の視点から、中古住宅購入時の注意点を「建物の状態」「土地と周辺環境」「契約」の3つの観点から解説します。 具体的なチェックポイントを参考に、理想の住まい探しを実現しましょう。
住宅診断(ホームインスペクション)とは?
住宅診断(ホームインスペクション)とは、専門家である住宅診断士が、第三者的な立場から住宅の状態を診断することです。この診断を受けると、建物の構造耐力上の安全性や劣化状況など、中古住宅のおおまかな情報を知ることができます。
ただし、インスペクションは目に見える劣化だけを見つける作業で、床下や屋根裏を詳細に調査することはしませんし、劣化の原因が何かを追究することもないので、出来れば耐震診断をおすすめします。
中古住宅を選ぶ際にチェックするポイント
中古住宅を選ぶ際は、以下の項目をチェックしておきましょう。
【耐震性を確認する】
中古住宅の耐震性は、建物の状態を判断する上で重要な要素です。とくに耐震性については、どの建築基準法の時代に建てられたかを確認することが大切です。2000年6月以降に建築確認申請された物件であれば、改正後の耐震基準で建てられているため、比較的安心だといえます。
それ以前に建設された建物の場合は、耐震診断を行うか、耐震補強工事済みの物件を選ぶことをおすすめします。
建築時の確認申請書類が残っている場合は、そちらを確認しましょう。「耐震基準適合証明書」や「住宅性能評価書」などの書類は、耐震基準を守って建設された証しです。
【建物の劣化状況を見る】
安心して中古住宅を購入するために、建物の劣化状況を確認しておくことが大切です。前述の住宅診断をおこなうことによって、欠陥中古住宅を購入するリスクを抑えることができます。また、目視で確認できる壁や床などは、細部まで状態をチェックしましょう。
【屋根の劣化状況を確認する】
屋根の劣化も、家全体の安全性と快適性に影響を与えます。屋根を上から見ることは現実的に難しいですが、もし目視できる範囲で劣化が見られた場合には、専門家による詳細な診断をおこないましょう。
下屋根を見れる場合は、ある程度の劣化状況が分かるので確認することをおすすめします。カビやコケが発生していないか、屋根の下地が見えていないかなど、セルフチェックしてみてください。
【電気設備のチェック】
中古住宅選びの際は、電気設備のチェックも怠らないようにしましょう。室内にある分電盤を見るとA(アンペア)の値が分かります。もし、アンペア数が不足していたり、何らかの不具合が見られる場合は、修繕費がかかることを想定しておきましょう。
中古住宅を購入する際の注意点
中古住宅を購入する際は、建物そのものだけでなく、周辺環境の確認も欠かせません。とくに以下の点に留意して住宅を選ぶとよいでしょう。
【災害リスクの確認】
中古住宅の購入時には災害リスクを考慮することが大切です。建物自体が良い物件だったとしても、浸水しやすいエリアだったり、地盤が弱いエリアだったりする可能性があります。そのため、ハザードマップを確認しておくことが大切です。
ハザードマップとは、該当地域にどのような災害のリスクがあるのかを地図に示したもので、地震・洪水・津波・高潮・土砂災害などのリスクが示されています。多くの自治体がハザードマップを作成しており、インターネット上でも確認できるので、ご自身でも検索してみてください。
【立地環境をチェック】
市場価格よりも明らかに安価な物件を見つけた場合、いくらお買い得だと感じても、注意が必要です。
安いのには何かしらの理由がある場合がほとんどでしょう。
例えば、公道に面している幅が2mより少ないと再建築不可物件となり、さまざまな工事に影響が出ます。次に売却する際も、なかなか売れないといったリスクがあります。そのほかには、土地に問題があったり(地盤が弱い、境界線トラブルがあるなど)、心理的瑕疵などの可能性もあります。
まとめ
中古住宅の購入は、新築に比べて価格が安く選択肢も多い反面、さまざまな点に注意が必要です。本記事で紹介したチェックポイントを参考に、物件選びを進めてください。
住宅診断の活用や、専門家への相談などを利用することで、中古住宅のリスクは軽減されます。適切な対策と情報収集をおこなうことで、後悔のない中古住宅購入を実現できるでしょう。
中古住宅の状態や耐震強度を知りたい方には、田口住生活設計室の「耐震診断」がおすすめです。床下に自ら潜って、しっかりと調査いたします。耐震診断の実績は累計1,000件以上。耐震診断なら、さいたま市の田口住生活設計室にお任せください。
耐震診断の詳細はこちらから>>>