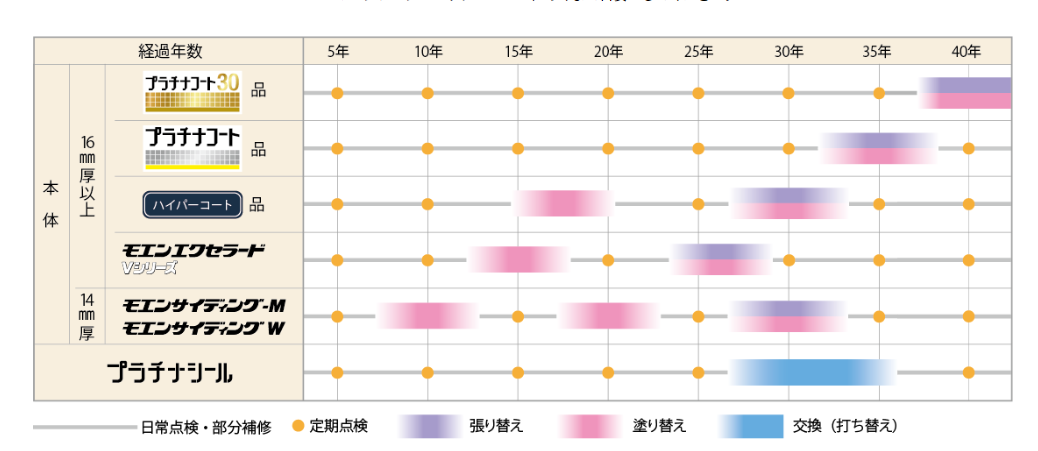2024.12.05
地震に強い家を作るために知っておきたい耐震リフォームの基礎
日本は地震が頻発する国であり、自宅の耐震性について不安を感じている方も少なくありません。特に築年数の経過した家に住んでいる場合は心配も大きいでしょう。
地震から身の危険を守るには、住宅の耐震リフォームが有効です。耐震リフォームを行うにあたって「地震に強い家」がどのようなものか、理解しておくことをおすすめします。
この記事では、耐震リフォームを考える際に知っておきたい地震に強い家の要素と、耐震診断の基本的な流れについて詳しく説明します。
地震から身の危険を守るには、住宅の耐震リフォームが有効です。耐震リフォームを行うにあたって「地震に強い家」がどのようなものか、理解しておくことをおすすめします。
この記事では、耐震リフォームを考える際に知っておきたい地震に強い家の要素と、耐震診断の基本的な流れについて詳しく説明します。
地震に強い家の3つの要素
地震に強い家を作るための基本的な要素は、大きく分けて以下の3つです。これらは耐震リフォームを考えるうえで押さえておきたいポイントです。
・壁の量
・壁のバランス
・接合部の強度
なお、本記事では木造の一般住宅を前提として解説します。
1. 壁の量
地震に強い家屋には、適切な「耐力壁」が必要です。耐力壁は筋交い(スジカイ)という斜めの材木が入っている壁のことで、家全体が倒壊しないよう支える役割を担っています。
耐震壁は一か所に偏らずに家全体にバランスよく配置されていることが理想です。筋交いの数が多ければ多いほど、家の耐震性が高まりますが、それだけで安心というわけではありません。耐震強度が高いかどうかは、壁全体の構造によって左右されます。
2.壁のバランス
家全体に耐力壁が十分にあっても、それが一か所に集中していたり、偏ったりしていると、地震の際に家の一部分に大きな力が集中してしまい、その部分が壊れるおそれがあります。
つまり、壁の配置がバランスの取れた状態になっていることが理想的なのです。耐震リフォームの際には、この「壁のバランス」を見直すことが大切な要素です。
3.接合部の強度
耐震に大きな影響を与えるのは、壁だけでなく「接合部」も同様です。接合部とは柱や梁、筋交いなどの建材同士がつながっている部分のことで、これらがしっかりしていないと、地震の揺れによって壁が外れたり、ずれたりするおそれがあります。
筋交いがしっかりと接合され、柱や梁とのつながりが強固であることが、家の耐震性を高めるポイントです。古い家の場合、釘や簡易的な金具で止められているだけのケースがあり、接合部がしっかりしていないことがあります。
耐震リフォームでは、これらの接合部を強化することによって、家の揺れに対する抵抗力を大幅に向上させることが可能です。
・壁の量
・壁のバランス
・接合部の強度
なお、本記事では木造の一般住宅を前提として解説します。
1. 壁の量
地震に強い家屋には、適切な「耐力壁」が必要です。耐力壁は筋交い(スジカイ)という斜めの材木が入っている壁のことで、家全体が倒壊しないよう支える役割を担っています。
耐震壁は一か所に偏らずに家全体にバランスよく配置されていることが理想です。筋交いの数が多ければ多いほど、家の耐震性が高まりますが、それだけで安心というわけではありません。耐震強度が高いかどうかは、壁全体の構造によって左右されます。
2.壁のバランス
家全体に耐力壁が十分にあっても、それが一か所に集中していたり、偏ったりしていると、地震の際に家の一部分に大きな力が集中してしまい、その部分が壊れるおそれがあります。
つまり、壁の配置がバランスの取れた状態になっていることが理想的なのです。耐震リフォームの際には、この「壁のバランス」を見直すことが大切な要素です。
3.接合部の強度
耐震に大きな影響を与えるのは、壁だけでなく「接合部」も同様です。接合部とは柱や梁、筋交いなどの建材同士がつながっている部分のことで、これらがしっかりしていないと、地震の揺れによって壁が外れたり、ずれたりするおそれがあります。
筋交いがしっかりと接合され、柱や梁とのつながりが強固であることが、家の耐震性を高めるポイントです。古い家の場合、釘や簡易的な金具で止められているだけのケースがあり、接合部がしっかりしていないことがあります。
耐震リフォームでは、これらの接合部を強化することによって、家の揺れに対する抵抗力を大幅に向上させることが可能です。
耐震診断の重要性と基本的な流れ
耐震補強を行う際には、床下や屋根裏に潜って構造部分を調査する、耐震診断を事前に行います。耐震診断を通じて自宅の現状を正確に把握し、どこを補強した方が良いのか明確にすることが可能です。
耐震診断の流れは以下のようになります。
1.事前のヒアリング
診断を行う前に、家の築年数や構造、過去の修繕履歴などをヒアリングします。まずは過去の改築歴を確認し、現在家主がどの部分に不安を感じているかを洗い出します。
また、今後リフォームしたいと考えている部分についても確認し、経済的に無理のない補強計画を策定します。事前にヒアリングをすることで、現地で目視チェックするポイントも把握しやすくなります。
2.現場調査
耐震診断の中心となるのが、実際に出向いて家屋を見る「現地調査」です。
この調査では、床下や屋根裏に入り、柱や梁の状態や筋交いの配置、接合部の強度などをチェックします。目視できない部分については、建築の知識や経験をもとにして診断を行います。
現地調査の際には、家屋の建築図面をあらかじめ確認しますが、古い家や中古で購入された場合は手元に図面がないこともあります。また、図面があってもその通りに建てられていないことは珍しくないので、実際に人の目で見て確認することが大切です。
3.点数による評価
調査結果は点数によって評価されます。
例えば、筋交いが十分に配置されている壁は高得点となり、反対に筋交いがない壁やバランスが悪い部分は評価が低くなります。
また、接合部がしっかりしていないところにも低い評価が与えられます。この点数によって、家全体の耐震性が数値化され、補強すべきポイントが明確になるのです。
4.報告書の作成と説明
診断結果の報告書には、具体的な補強方法やリフォームの優先順位が記載されます。報告書をもとに、補強部分や補強方法、必要になる予算などが算出されます。
耐震診断の報告書は、単に点数を提示するのではなく、その点数の根拠を具体的に示しているかが肝心です。報告書をもとに、耐震リフォームの提案が行われることが一般的です。
耐震診断の流れは以下のようになります。
1.事前のヒアリング
診断を行う前に、家の築年数や構造、過去の修繕履歴などをヒアリングします。まずは過去の改築歴を確認し、現在家主がどの部分に不安を感じているかを洗い出します。
また、今後リフォームしたいと考えている部分についても確認し、経済的に無理のない補強計画を策定します。事前にヒアリングをすることで、現地で目視チェックするポイントも把握しやすくなります。
2.現場調査
耐震診断の中心となるのが、実際に出向いて家屋を見る「現地調査」です。
この調査では、床下や屋根裏に入り、柱や梁の状態や筋交いの配置、接合部の強度などをチェックします。目視できない部分については、建築の知識や経験をもとにして診断を行います。
現地調査の際には、家屋の建築図面をあらかじめ確認しますが、古い家や中古で購入された場合は手元に図面がないこともあります。また、図面があってもその通りに建てられていないことは珍しくないので、実際に人の目で見て確認することが大切です。
3.点数による評価
調査結果は点数によって評価されます。
例えば、筋交いが十分に配置されている壁は高得点となり、反対に筋交いがない壁やバランスが悪い部分は評価が低くなります。
また、接合部がしっかりしていないところにも低い評価が与えられます。この点数によって、家全体の耐震性が数値化され、補強すべきポイントが明確になるのです。
4.報告書の作成と説明
診断結果の報告書には、具体的な補強方法やリフォームの優先順位が記載されます。報告書をもとに、補強部分や補強方法、必要になる予算などが算出されます。
耐震診断の報告書は、単に点数を提示するのではなく、その点数の根拠を具体的に示しているかが肝心です。報告書をもとに、耐震リフォームの提案が行われることが一般的です。
耐震補強の優先順位とリフォームの進め方
耐震診断の結果をもとにリフォームを進める際には、予算や工期を考慮したうえでリフォーム計画を立てましょう。
最もリスクの高いところから耐震補強を行うことが肝心で、特に接合が弱い部分や、バランスが大きく崩れている部分にも着手しましょう。
耐力壁の量が不足している場合は補強を行うことで大幅に耐震性が向上します。補強を行うことで、家全体の耐震性を向上させ、地震に対して安心できる住まいを実現することが可能になります。
最もリスクの高いところから耐震補強を行うことが肝心で、特に接合が弱い部分や、バランスが大きく崩れている部分にも着手しましょう。
耐力壁の量が不足している場合は補強を行うことで大幅に耐震性が向上します。補強を行うことで、家全体の耐震性を向上させ、地震に対して安心できる住まいを実現することが可能になります。
費用と工期の目安
耐震診断の目安金額は、30坪までの家で16万5,000円(税込)~です。それより大きな家は1坪あたり5,500円(税込)が追加になり、料金のなかには「現地調査」「診断書作成」「診断書の説明」「補強計画案策定」などが含まれています。
実際に耐震リフォームを行う場合、補強箇所にもよりますが50~200万円程度まで、建物によって大きく異なります。たとえば、壁に金属製の補強材を入れる場合は、1間の壁で27万5,000円(税込)〜が目安です。※1間=約1.82m
たくさんの耐力壁を作れば強い家になりますが、当然費用は掛かります。最優先箇所だけを補強する方法も可能なため、予算に合わせて施工してもらえるようにリフォーム会社に相談しましょう。
耐震補強にかかる工期も、工事規模によって大きく異なります。上記で挙げた1間の壁補強の例であれば、3日~1週間程度が目安です。
間取りや面積、築年数によって費用が変わるため、実際に見てみないと正確な工期や金額は算出できません。詳しい費用や工期を知りたい方は、リフォーム会社に見積りを依頼してください。
実際に耐震リフォームを行う場合、補強箇所にもよりますが50~200万円程度まで、建物によって大きく異なります。たとえば、壁に金属製の補強材を入れる場合は、1間の壁で27万5,000円(税込)〜が目安です。※1間=約1.82m
たくさんの耐力壁を作れば強い家になりますが、当然費用は掛かります。最優先箇所だけを補強する方法も可能なため、予算に合わせて施工してもらえるようにリフォーム会社に相談しましょう。
耐震補強にかかる工期も、工事規模によって大きく異なります。上記で挙げた1間の壁補強の例であれば、3日~1週間程度が目安です。
間取りや面積、築年数によって費用が変わるため、実際に見てみないと正確な工期や金額は算出できません。詳しい費用や工期を知りたい方は、リフォーム会社に見積りを依頼してください。
まとめ
地震による家屋の倒壊が心配な人は、耐震診断を受けることがおすすめです。診断結果に基づき、適切なリフォームを行えば、家屋の安全性が向上します。耐震診断を依頼する際には、的確な診断を行ってくれる業者に依頼しましょう。
田口住生活設計室では、豊富な経験を活かし正確な診断と、適切な補強計画をご提案します。安心して住み続けられる家を手に入れるために、耐震リフォームの第一歩を踏み出しましょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
田口住生活設計室では、豊富な経験を活かし正確な診断と、適切な補強計画をご提案します。安心して住み続けられる家を手に入れるために、耐震リフォームの第一歩を踏み出しましょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::