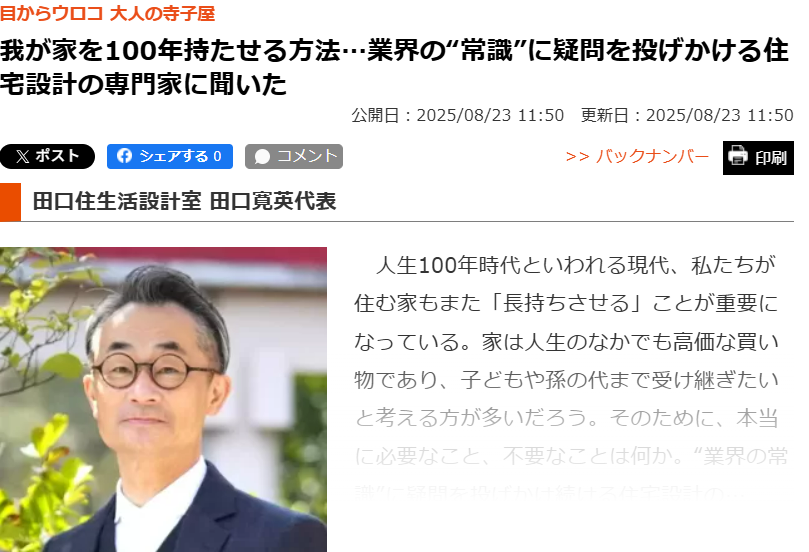2025.10.12
無料セミナー開催のお知らせ│10月18日(土)安心するための耐震セミナー@さいたま市

田口住生活設計室より、セミナー開催のお知らせです。
毎回ご好評いただいている、耐震セミナーを再び、さいたま市にて開催いたします!自宅の耐震性に不安のある方や、正しい知識を身につけたい方は、ぜひご参加ください。
■ 開催概要
日時: 2025年10月18日(土) 9:30~11:30 (9:20受付開始)
場所: 岩槻東口コミュニティセンター 2階 会議室A
参加費: 100円 (資料代)
参加方法: 事前予約は不要です。当日、直接会場へお越しください。
■ セミナーの内容
・どのような家が壊れやすいのか
・必要な耐震工事と費用の目安
・専門家による診断書の正しい読み方
・耐震補強を口実にした悪質な詐GIの実例と対策
現場経験豊富な建築士が、実体験にもとづいて具体的に解説します。
たくさんのご参加、お待ちしております!
■ 主催・お問い合わせ
一般社団法人 安心と住まいのGメン
TEL: 048-729-8100
2025.10.11
階段上のデッドスペースを収納に!活用アイデアや安全性確保のポイント

家の中を改めて見渡してみると、意外と活用しきれていない「デッドスペース」があることに気づくかもしれません。
特に、階段を上がった先のホールや踊り場は、ただの通路としてしか使われていないことが多いのではないでしょうか。しかし、その何気ない空間こそ、暮らしを豊かにする大きな可能性を秘めているのです。
今回は、階段上のデッドスペースを便利で魅力的な収納空間に変えるためのアイデアやポイントをご紹介します。
階段上のデッドスペースを収納に活用するメリット
1.家全体の収納力を底上げできる
住まいの悩みで常に上位に挙がるのが、収納不足の問題です。これまで見過ごされてきた階段上のスペースを収納として活用することで、家全体の収納力を純粋に底上げできます。
新たに収納家具を置く場所がないと諦めていた方でも、このスペースを使えばクローゼットや押し入れに入りきらない物をしまう場所を生み出せるのです。結果として、家全体の整理整頓がはかどるでしょう。
2.動線との組み合わせで便利な収納に
階段は、1階と2階をつなぐ、家族が毎日必ず通る場所です。その生活動線上にある収納は、驚くほど便利な存在になります。
例えば、家族みんなが使うタオルやパジャマを置くファミリークローゼットとして使えば、洗濯物をしまうのも、お風呂上がりに取り出すのもスムーズです。ただ物をしまう場所ではなく、「使う場所の近くに置く」という効率的な収納が実現します。
3.空間を有効活用できる満足感
デッドスペースだった場所が、アイデア一つで機能的な空間に生まれ変わる。この変化は、物理的な利便性だけでなく、大きな満足感をもたらしてくれます。
今まで「もったいない」と感じていた空間が活かされることで、家全体がすっきりと整った印象になります。「無駄なスペースがなくなった」という達成感は、家づくりやリフォームの大きな喜びの一つになるはずです。
階段上のデッドスペース向け収納アイデア
1.通路を兼ねたファミリークローゼットとしての収納
階段を上がった先のホールが広い場合におすすめなのが、家族全員分の衣類などをまとめて管理できるファミリークローゼットです。壁一面にハンガーパイプや棚を設置すれば、大容量の収納スペースが生まれます。
あえて扉をつけないオープンクローゼットにすれば、通路としての開放感を保ちつつ、ショップのディスプレイのようなおしゃれな空間を演出することも可能です。
2.本や小物を置くための壁面収納
本好きの家庭なら、階段周りの壁面をライブラリーに変えてみてはいかがでしょうか。壁に造り付けの本棚を設置すれば、まるで図書館のような空間が生まれます。
本棚は奥行きをそれほど必要としないため、通路の幅を大きく狭めることなく、驚くほど多くの本を収納できます。家族の成長と共に増えていく本を美しく整理できる、実用性とインテリア性を兼ね備えたアイデアです。
3.季節飾りなどを楽しむディスプレイスペースとしての収納
収納は、必ずしも物を隠すためだけのものではありません。壁の一部をへこませた「ニッチ」と呼ばれる飾り棚や、腰高のカウンターを設ければ、そこは家族の思い出や季節の飾りを楽しむ特別なスペースに変わります。
雛人形や五月人形、クリスマスやお正月の飾りなど、季節ごとのイベントを彩る場所として活用するのです。毎日通る場所だからこそ、暮らしに潤いを与えてくれるディスプレイスペースは、生活をより豊かなものにしてくれます。
階段上のデッドスペースに収納を作る際の注意点
1.安全第一!階段上の収納で最も重要な耐荷重
階段上のスペースに収納を設ける際、何よりも優先しなければならないのが安全性です。特に、後からリフォームで床を拡張して収納を作る場合は、その床がどのくらいの重さに耐えられるかという「耐荷重」の確認が不可欠です。
本棚のように重量のあるものを大量に置く計画であれば、床の補強工事が必要になることも少なくありません。計画段階で必ず建築士や施工会社などの専門家に相談し、構造上の安全性を確保しましょう。
また、階段付近にものが出ている状態だと、災害時に急いで外に出る際の障害となることも。いざというときのことも考えて、できるだけすっきり収納しましょう。
2.デッドスペースでも圧迫感を生まない収納計画
せっかく収納を増やしても、そのせいで空間が狭く感じたり、暗くなったりしては快適さが損なわれてしまいます。圧迫感を生まないためには、いくつかの工夫が有効です。
例えば、収納棚の色を壁の色と統一して存在感を和らげたり、背板のないオープンな棚を選んで視線の抜けを作ったりするだけでも印象は大きく変わります。また、照明計画も同時に考え、手元や足元が暗くならないよう配慮することも大切です。
3.階段上の収納における日々の生活動線への配慮
階段やその周辺は、人や物がスムーズに行き来するための重要な通路です。収納を設けることで、この「動線」を妨げてしまわないよう、計画は慎重に行う必要があります。
さらに、将来的に大きな家具を2階へ搬入する際の経路として問題ないか、といった長期的な視点も持って計画を進めましょう。
まとめ
これまで見過ごされがちだった階段上のデッドスペースは、アイデア次第で暮らしを豊かにする価値ある収納空間へと生まれ変わります。
家族の衣類をまとめるクローゼットから、知的好奇心を満たす壁面ライブラリー、暮らしに彩りを添えるディスプレイスペースまで、その可能性は無限です。専門家のアドバイスも参考にしながら、あなたのご家庭に最適な活用法を見つけましょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.10.04
TOTO CONNECT PUBLICとは?パブリックトイレ管理の課題をデータで解決

私たちの暮らしにとって欠かせない存在であるトイレが、今、技術によって大きく変化しようとしています。
例えば、日常的に利用する公共施設のトイレでは、利用者の目に見えないところで、長年にわたって多くの管理上の課題が積み重なってきましたが、そうした問題が、新しい取り組みによって解決されようとしています。
一方で、家庭内に設置されたプライベートなトイレは、今までの役割を超えて、私たちの健康状態を日々チェックする新たな役割を担おうとしています。
今回は、こうしたトイレの最新技術と革新的な取り組みに焦点を当て、私たちの暮らしにどのような価値をもたらすのかをご紹介します。
パブリック(公共空間における)トイレの課題とは?
【データ不在による場当たり的な管理計画】
これまで多くの公共トイレでは、清掃やメンテナンスのスケジュールが明確なデータに基づくものではなく、長年の現場経験や担当者の勘に頼ることが一般的でした。
例えば、1日を通じてほとんど人が訪れないトイレと混雑する駅構内や商業施設のトイレを同じ頻度で巡回・清掃されるケースが多く、効率的な管理とは言い難い状況が続いていました。
その結果、汚れが集中する時間帯に対応が間に合わず、衛生環境が悪化する一方で、利用者の少ない時間帯には過剰な清掃作業が発生するといった、無駄と非効率の二重苦が現場を悩ませていました。
データという客観的で再現性のある指標が欠如していたため、管理計画を最適化することが困難だったのです。
【クレームで発覚する消耗品切れや故障】
「トイレットペーパーが補充されていない」「石鹸ディスペンサーが空だった」といった利用者のクレームによって、初めてトラブルが明るみに出るというケースは非常に多く見られます。
これは、消耗品の残量確認が目視に頼っていたことや、定期的なチェック体制が整っていなかったことが原因です。
また、便器の詰まりや水の流れ不良、ウォシュレットの不具合などの機器の故障も、実際にユーザーが不便を感じるまで発見されないことが一般的でした。
こうした状況は、利用者にとっては不快な体験であると同時に、施設管理者にとっても迅速な対応を迫られるストレスの大きな要因となっています。
【清掃スタッフの負担増と人手不足】
社会全体で進行する人手不足の波は、トイレ清掃業務にも大きな影響を与えています。
特に都市部の大型商業施設や公共施設では、広い敷地内に多数のトイレが存在し、それぞれを日常的に清潔に保つためには、相応の人的リソースが必要です。
しかし現実には、限られた人数のスタッフが多くの業務を抱えており、一人ひとりへの業務負担が年々重くなっています。
クレーム対応に追われたり、汚れていない場所への無駄な巡回を繰り返すうちに、スタッフのモチベーションが低下し、離職につながるケースも少なくありません。
TOTO CONNECT PUBLICが提供する解決策
【トイレの利用状況をデータで可視化】
TOTO CONNECT PUBLICでは、最新のIoT技術を活用することで、トイレの個室ごとの利用回数や滞在時間、使用頻度などをリアルタイムで取得できるシステムを導入しています。
これにより、例えば「平日夕方の駅構内トイレが混雑しやすい」「週末は観光施設の女性トイレに利用者が集中する」といった具体的な傾向をデータとして可視化でき、効率的な運用が可能になります。
決まった時間に巡回するのではなく、「どこで・いつ・どの程度利用されているか」という情報に基づいて、最も必要なタイミングで的確な対応を行うことができるようになります。
【機器の稼働状況を遠隔でモニタリング】
トイレ内に設置されたセンサー群は、便器の洗浄機能や手洗い場の水流など、主要設備の動作状況を24時間365日監視しています。
これにより、「水が止まらない」「ウォシュレットが作動しない」などの異常を瞬時に検知し、管理者にアラート通知を送る仕組みが構築されています。
異常を現場で発見する前に、遠隔で状況を把握できることで、迅速な初期対応が可能となり、トラブルの拡大を未然に防ぐことができます。
【データに基づいた効率的な清掃計画】
これまでの画一的な巡回清掃ではなく、利用実績のデータに基づいて清掃計画を組み立てることで、より効率的で負担の少ない業務体制を実現できます。
たとえば、大型イベント開催時や繁忙期には、特定の時間帯に利用者が急増する傾向があります。
そうした時期には、通常よりも多くのスタッフをそのエリアに配置するなど、柔軟で効果的なリソース配分が可能となります。
これにより、常に清潔で快適な環境を提供しつつ、清掃スタッフの労力を最小限に抑えることができます。
【消耗品の補充タイミングを的確に通知】
トイレットペーパーや便座クリーナー、液体石鹸などの消耗品の残量をセンサーで常時監視し、あらかじめ設定された閾値を下回った際に、管理者のスマートデバイスに自動通知を送信します。
これにより、スタッフは「補充が必要かどうか」を都度確認する手間が省け、効率的な補充作業が可能になります。
さらに、利用者が不快な思いをする前に対応が完了するため、クレームの予防と利用満足度の向上を同時に実現できます。
TOTOの便スキャンとは?
【日々の排泄物から健康状態をチェック】
公共トイレがスマート化する中で、家庭用トイレもまた、高度な健康モニタリング機能を持つ“パーソナルヘルスステーション”へと進化を遂げています。
TOTOが開発した「便スキャン」は、利用者が普段どおりにトイレを使用するだけで、便の状態(形状・量・色など)をAIが解析し、その人の健康状態をチェックする先進的な技術です。
この技術は、日々の食事や生活習慣の変化が身体に与える影響を、排泄物という最も正直なバロメーターを通して可視化する点に特徴があります。
【スマートフォンアプリとの連携】
便スキャンで得られたデータは、専用のスマートフォンアプリと自動的に連携され、過去の記録とともに一覧で確認することが可能です。
毎日の便の変化をアプリが蓄積してくれるため、ユーザーは特に意識しなくても、自分自身の健康の傾向を長期的に把握できるようになります。
アプリは視覚的に分かりやすいグラフやコメントでフィードバックを行い、ユーザーの健康への関心を自然と高めてくれます。
【未病の段階で気づきを促す】
便スキャンは医療機器ではないため病気の診断を行うものではありませんが、体の変化をいち早く察知する“気づき”のきっかけを提供するツールとして期待されています。
たとえば、便秘や下痢など軽度な不調が続くことで、食生活を見直したり、運動習慣を取り入れたりと、生活全体をより健康的な方向に調整する動機づけになります。
トイレに座るという日常の行為が、自分自身の健康と向き合う貴重な時間へと変わっていくのです。
まとめ
公共トイレの管理は、IoTやAIといった先進技術の導入により、データに基づいた効率的かつ持続可能な形に進化しつつあります。
それによって、清掃スタッフの負担を軽減しながら、利用者にとって常に快適で清潔な空間を提供できる新しいインフラが今後実現するとされています。
そして家庭では、トイレが私たちの健康状態を日々見守るパートナーとしての役割を担うようになり、予防医療の観点からもその存在価値が再評価されています。
私たちの生活に密接に関わるトイレは、今後もさらなる進化を遂げていき、暮らしの質を高める重要な存在として注目され続けるでしょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.10.01
Low-Eガラスの効果とは?暑さ寒さをコントロールして室内の快適性を高める

窓ガラス一枚で、部屋の快適さが大きく変わることをご存知でしょうか。
特に、夏の日差しの強さや冬の底冷えは、窓の性能に大きく左右されます。
近年注目されている「Low-Eガラス」は、そんな住まいの悩みを解決する選択肢の一つです。
このガラスには性能の異なる2つのタイプがあり、どちらを選ぶかが快適な暮らしの鍵を握ります。
本記事では、Low-Eガラスの基本的な特徴から、タイプごとの効果の違い、そして最適な選び方までを解説します。
Low-Eガラスとは?複層ガラスとの違い
・複層ガラスに特殊な金属膜を追加した構造
Low-Eガラスを理解するには、まず複層ガラスについて知る必要があります。
複層ガラスとは、2枚のガラスを重ね、その間に乾燥した空気やガスを封じ込めた構造のガラスのことです。
Low-Eガラスは、この複層ガラスをベースに、ガラスの内側に「Low-E膜」と呼ばれる特殊な金属膜をコーティングしたものです。
この金属膜は非常に薄く、人の目には見えないため、窓の透明性を損なうことはありません。
・夏と冬で効果を発揮する「遮熱」と「断熱」
Low-E膜が持つ最大の特長は、熱の伝わり方をコントロールできる点にあります。
具体的には、太陽光に含まれる熱(赤外線)や、室内で発生する暖房の熱などを反射する性質を持っています。
そのため、夏は屋外の太陽熱が室内へ侵入するのを防ぎ(遮熱効果)、冬は室内の暖かい熱が窓から逃げていくのを防ぐ(断熱効果)という、二つの役割を果たします。
季節を問わず、快適な室温を保つ手助けをしてくれるのです。
・複層ガラスを超える高い省エネ効果
Low-Eガラスは、特殊な金属膜を持たない一般的な複層ガラスと比較して、格段に高い遮熱性と断熱性を誇ります。
窓からの熱の出入りが少なくなることで、冷暖房の効率が大幅に向上します。
これにより、エアコンの設定温度を過度に上げ下げする必要がなくなり、結果として年間の光熱費を抑えることにつながります。
つまり、初期費用はかかりますが、長期的に見れば経済的なメリットも期待できるのです。
遮熱タイプと断熱タイプの効果の決定的な違い
・Low-Eガラスには2つのタイプがある
一口にLow-Eガラスと言っても、実は「遮熱タイプ」と「断熱タイプ」という2つの種類が存在します。
どちらのタイプもLow-E膜を利用している点は同じですが、その効果は大きく異なります。
この違いを生み出しているのは、複層ガラスのどの面にLow-E膜がコーティングされているかという、膜の位置の違いです。
このわずかな構造の違いが、それぞれの性能を決定づけています。
・遮熱タイプ:夏の日差しと熱を強力にカットする効果
遮熱タイプは、Low-E膜を室外側のガラスの室内側面に配置しています。
この構造により、太陽の熱を室内に入る前に効率よく反射させることが可能です。
特に、真夏の強い日差しや西日による室温の上昇を強力に抑える効果があります。
そのため、冷房の効きが良くなり、暑い季節でも涼しく快適に過ごしたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。
日差しが強く室温が上がりやすい南向きや西向きの窓に適しています。
・断熱タイプ:冬の室内の暖かさを外に逃がさない効果
一方、断熱タイプはLow-E膜を室内側のガラスの室外側面に配置したものです。
このタイプは、太陽の暖かさをある程度室内に取り込みつつ、一度暖まった室内の空気が外へ逃げるのを防ぐ効果に優れています。
暖房の熱を窓際でしっかり守るため、冬の寒さが厳しい環境や、暖房効率を重視したい場合にその真価を発揮します。
例えば、日当たりの良い南向きの窓であれば、暖かい空気を室内に閉じ込めてくれます。
反対に、日当たりの弱い北側の窓であれば、断熱性を高めることで室温の低下を防ぐことができます。
どちらを選ぶべき?方角や目的別の比較と選び方
・夏の西日が厳しい窓には「遮熱タイプ」
もし、特定の窓からの日差しに悩まされているのであれば、その方角に合わせてタイプを選ぶのが賢明です。
例えば、夏の午後になると強烈な西日で部屋が灼熱地獄のようになる、という窓には「遮熱タイプ」が最適です。
太陽熱を強力にカットするため、室温の上昇を大幅に緩和できます。
日差しが強い南向きの窓にも同様の効果が期待できるでしょう。
・冬の寒さが厳しい北側の窓には「断熱タイプ」
日当たりが悪く、冬になると窓際からひんやりとした冷気を感じる北側の窓。
こうした場所には「断熱タイプ」が適しています。
室内の暖房熱を外に逃がさない保温効果が高いため、足元の冷えを和らげ、結露の発生を抑制する助けにもなります。
暖房をつけてもなかなか部屋が暖まらない、といった悩みを解決してくれます。
・年間通してバランスの取れた効果を求めるなら「断熱タイプ」
特定の方角や季節に強い悩みがあるわけではなく、家全体で年間を通じた快適性を求める場合には、「断熱タイプ」がバランスの取れた選択肢となることが多いです。
断熱タイプは、冬の寒さを防ぐ効果を主としながらも、一定の遮熱効果も併せ持っています。
そのため、夏の厳しい日差しはある程度和らげ、冬は暖かさを保つという、一年を通じた快適な住環境づくりに貢献します。
まとめ
Low-Eガラスは、複層ガラスの性能を特殊な金属膜で向上させた高機能ガラスです。
その最大の特徴は、夏と冬の両方で室内の快適性を高める力にあります。
「遮熱タイプ」は夏の強い日差しと熱を防ぐことに特化しており、西日が厳しい窓などに最適です。
一方、「断熱タイプ」は冬の暖かさを室内に留める効果が高く、北側の窓や寒冷地で活躍します。
窓の方角やご家庭の悩みに合わせて適切なタイプを選ぶことが、一年中快適で省エネな暮らしを実現するための重要なポイントです。
窓のリフォームで快適な暮らしを実現しましょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.09.27
バスタブのサイズは何センチあれば足が伸ばせる?サイズと形状を紹介

一日の終わりに、湯船にゆっくりと浸かる時間は格別なものです。どうせなら足を伸ばして、心ゆくまでリラックスしたいと考えるのは自然なことでしょう。
しかし、ただ大きいだけのバスタブが、必ずしも快適さや安全性につながるとは限りません。実は、バスタブのサイズ選びには、見落としがちなポイントがいくつか存在します。今回は、あなたのバスタイムをより豊かにするための、バスタブ選びのヒントをご紹介します。
足を伸ばせるバスタブのサイズの基本
1.足を伸ばすために必要なバスタブの内寸サイズとは?
快適な入浴の鍵を握るのは、バスタブの「内寸」です。大人が膝を軽く曲げてリラックスできるサイズとしては、内寸の長さが110cm〜120cm以上あると良いとされています。
これは身長に関わらず、多くの方が足を伸ばせると感じられる大きさの目安です。バスタブ製品を選ぶ際は、外側のサイズだけでなく内寸も忘れずにチェックしましょう。
2.一般的なユニットバスのサイズ表記と浴槽サイズの関係
リフォームや新築の際によく目にする「1216」や「1616」といった数字。これはユニットバス全体のサイズを示す規格です。たとえば「1216」の場合、浴室の内寸が120cm×160cmであることを意味します。
この数字はあくまで浴室の大きさを表しており、バスタブのサイズに比例するとは限りません。最終的な浴槽のサイズは、製品のデザインや洗い場の広さとの兼ね合いで決まるため、表示されている規格サイズだけで判断しないようにしましょう。
3.【身長別】足が伸ばせるバスタブのサイズ目安
・身長160cm前後の方
内寸110cm程度でも、十分に足を伸ばしてくつろげます。
・身長170cm前後の方
内寸120cm程度あると、膝をゆったりと伸ばせるでしょう。
・身長180cm以上の方
内寸130cm以上を目安にすると、窮屈さを感じにくいです。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、座高や好みの姿勢によっても体感は変わります。可能であれば、ショールームなどで実際に浴槽に入ってみることがおすすめです。
サイズ感に影響するバスタブの形状
1.直線的で足が伸ばしやすいストレート浴槽
最もスタンダードな形状が、壁面が直線的になっているストレート浴槽です。このタイプは、浴槽の底面が広く、デッドスペースが生まれにくいため、足をまっすぐ伸ばしやすいという大きなメリットがあります。シンプルなデザインはどんな浴室にも馴染みやすく、広々とした入浴感を求める方には最適な選択肢と言えるでしょう。
2.節水もできるSライン浴槽
浴槽の内側が緩やかなS字カーブを描いているのがSライン浴槽です。この形状は体にフィットしやすく、少ないお湯の量でも肩までしっかりと浸かれるため、節水効果が期待できます。
デザイン性も高く人気がありますが、曲線的な分、ストレート浴槽に比べると足を伸ばすためのスペースはやや狭く感じるかもしれません。
3.親子でも入れるワイド浴槽
洗い場側に浴槽の一部が張り出している形状のワイド浴槽。その名の通り、洗い場側のスペースにステップが設けられていることが多く、半身浴を楽しんだり、小さなお子さんと一緒に入浴したりするのに便利です。
家族でのバスタイムを重視する方には魅力的ですが、その分洗い場が狭くなるため、浴室全体の広さとのバランスを慎重に考える必要があります。
4.節水と安全性を両立するベンチ付き浴槽
浴槽内に段差(ベンチ)が設けられているタイプで、「腰かけ付き浴槽」とも呼ばれます。この段差の分だけ必要なお湯の量を減らせるため、高い節水効果が期待できます。
ベンチに腰掛けて気軽に半身浴を楽しんだり、小さなお子様の出入りのためのステップにしたりと、様々な使い方ができるのが魅力です。段差のない深い側では大人も足を伸ばして入浴できます。また、ベンチに座ることで安定した姿勢が保てるため、浮力で身体が滑ってしまう危険性が少ないという安全面のメリットもあります。
快適なサイズのバスタブを選ぶためのポイント
1.浴室全体のサイズとバスタブの最適なバランス
理想のバスタブを見つけても、浴室全体のバランスを無視してはいけません。特に重要なのが、体を洗ったり掃除をしたりする「洗い場」のスペースです。大きなバスタブを設置した結果、洗い場が極端に狭くなり、日々の使い勝手が悪くなっては本末転倒です。
一般的に、洗い場の幅は最低でも80cm以上確保することが望ましいとされています。バスタブと洗い場、両方の快適性を考えたサイズ選びが後悔しないための鍵です。
2.足が伸ばせるサイズでも注意したい浴槽の深さ
足を伸ばせる広い浴槽は魅力的ですが、安易に選ぶと思わぬ危険が潜んでいます。実は、「足を伸ばせること」が絶対に良いわけではないのです。
広すぎる浴槽では、お湯の浮力で体が安定せず、滑って溺れてしまうリスクがあります。特に高齢者の場合、浴槽の向こう側に足が届くことで体をしっかりと支えられ、溺れる危険性が大幅に減ります。
また、浴槽の深さも重要で、深すぎると出入りの際にバランスを崩しやすく、転倒の危険も。リラックスのためのはずが事故の原因にならぬよう、安全性という視点も、バスタブ選びには不可欠です。
3.家族構成で考える後悔しないバスタブのサイズ選び
バスタブ選びは、今の暮らしだけでなく、将来の家族構成の変化も見据えて行うことが大切です。たとえば、小さなお子さんがいるご家庭なら、一緒に安全に入れるワイド浴槽が活躍するでしょう。一方、ご高齢の家族がいる、あるいは将来の自分たちのためには、手すりが付けやすく、またぎやすい高さで、かつ足が壁に届くような安全性を重視したモデルが安心です。
一人暮らしであれば、お湯がすぐに溜まり掃除もしやすいコンパクトなタイプが合理的かもしれません。家族みんなが快適に、そして安全に使えるバスタブを選びましょう。
まとめ
足を伸ばしてくつろげるバスタブを選ぶには、まず内寸で110cm以上を目安にしてみましょう。ユニットバスの規格サイズと浴槽のサイズは違うことを理解し、身長や好みに合ったものを見極める必要があります。
この記事でご紹介したポイントを参考に、あなたとご家族にとって最適なバスタブを見つけてください。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.09.20
トイレはTOTOとリクシルどっち?機能やデザイン、選び方を解説

トイレのリフォームは、日々の暮らしの快適さを大きく左右する重要な選択です。なかでも国内のトイレ市場で大きなシェアを占めるTOTOとリクシルは、多くの人が比較検討する2大メーカーではないでしょうか。
そこで今回は、TOTOとリクシルのトイレをさまざまな角度から比較し、あなたに最適なトイレを見つけるためのヒントをご紹介します。
TOTOとリクシル、トイレの基本的な違い
ここでは、それぞれのメーカーの特徴を解説します。
1.トイレの王道メーカー「TOTO」の特徴とは
TOTOは、1917年に東洋陶器株式会社として創立された、衛生陶器のパイオニアです。その名の通り、陶器製の便器づくりから始まった歴史を持ち、品質と技術力で業界をリードしてきました。
「ウォシュレット」という言葉を世に広めたことでも知られ、長年の研究開発に裏打ちされた高い機能性と品質へのこだわりが最大の特徴です。
とくに「きれい除菌水」に代表される独自の清潔技術は、衛生面を重視するユーザーから絶大な支持を集めています。機能性を第一に考え、信頼と実績のあるブランドを選びたいという方に、まず検討してほしいメーカーです。
2.デザイン性に強みを持つ「リクシル」の特徴とは
リクシルの前身であるINAXは、1924年に伊奈製陶株式会社として創立されました。タイル製造から事業を始め、のちに衛生陶器の分野へ進出した背景があります。
そのため、トイレだけでなくキッチンや窓など住宅設備を幅広く手掛けるのがリクシルです。トータルコーディネートを得意とする同社は、トイレ単体だけでなく、空間全体を美しく見せるデザイン性の高さに強みを持ちます。
もちろん機能面も抜かりなく、汚れがつきにくい新素材「アクアセラミック」はリクシルを代表する技術の一つです。トイレをインテリアの一部として考え、デザインにもこだわりたいというニーズに応えてくれます。
3.TOTOとリクシルのトイレ、価格帯はどう違う?
価格については、両社とも幅広いニーズに応えるため、手頃な普及価格帯から多機能なハイグレードモデルまで、多彩なラインナップを揃えています。そのため、一概にどちらが高い・安いと断言することはできません。
しかし、同じような機能を持つ同等のグレードで比較した場合、リクシルの方がやや価格を抑えたモデルが見つかりやすい傾向があります。ただし、最終的な価格は搭載機能やシリーズによって大きく変動するため、予算に合わせてそれぞれの製品を比較検討することが重要です。
【清掃性で比較】TOTOとリクシルのトイレ、掃除しやすいのはどっち?
1.素材で比較!TOTO「セフィオンテクト」とリクシル「アクアセラミック」
【TOTO】
TOTOが誇る技術が、陶器表面の凹凸をナノレベルまで滑らかにした「セフィオンテクト」です。これにより、汚れが付きにくく、落としやすい状態を長期間保ちます。
【リクシル】
リクシルは、そもそも汚れの原因となる水アカの固着を防ぐ新素材「アクアセラミック」を開発しました。こちらは新品のツルツル感が100年続くとうたわれており、汚物汚れも水の力で浮かせて洗い流します。
どちらも高い防汚性能を持ちますが、アプローチの仕方が異なります。
2.フチの形で比較!TOTOとリクシルのトイレ、汚れにくいのはどっち?
掃除の手間を大きく左右するのが、便器のフチの形状です。かつては掃除のしにくいフチ裏がありましたが、今やフチなしが主流です。
【TOTO】
TOTOは「スゴフチ」と呼ばれる滑らかなフチなし形状を採用しており、汚れてもサッとひと拭きで掃除が完了します。
【リクシル】
リクシルも「フチレス形状」で、フチを丸ごとなくした大胆なデザインが特徴です。どちらも従来のトイレに比べて格段に掃除がしやすくなっており、甲乙つけがたい進化を遂げています。
3.除菌機能で比較!TOTO「きれい除菌水」とリクシル「プラズマクラスター」
清潔さを保つための独自機能も、両社の大きな違いです。
【TOTO】
TOTOの「きれい除菌水」は、水道水を電気分解して作られる除菌成分を含んだ水のことです。使用後に便器内やウォシュレットのノズルに自動で吹きかけ、目に見えない菌の繁殖を抑えます。
【リクシル】
リクシルは、シャープの「プラズマクラスターイオン」技術を採用しています。イオンの力で便座からタンク、さらにはトイレ空間に浮遊するカビ菌まで除菌し、ニオイの発生も防ぎます。
【機能・デザインで比較】TOTOとリクシルのトイレ、満足度が高いのはどっち?
1.洗浄方式で比較!TOTOとリクシルのトイレ、節水力と洗浄力はどっちが上?
節水と洗浄力の両立も、現代のトイレ選びの重要ポイントです。
【TOTO】
TOTOは、渦を巻くような水流で便器内を洗い流す「トルネード洗浄」が特徴です。少ない水量でも効率的に洗浄できるうえ、便器のフチ裏をなくした「フチなし形状」により、汚れがつきにくく掃除がとても楽になっています。
【リクシル】
リクシルは、3つの吐水口から強力な水流を発生させる「パワーストリーム洗浄」を採用しています。こちらも少ない水で、便器の隅々までしっかりと洗い流す力を誇ります。
洗浄方式は異なりますが、どちらも高いレベルで節水と洗浄を両立しています。
2.デザイン性で選ぶトイレならTOTOとリクシルどっち?
デザインの好みは人それぞれですが、両社には異なる傾向が見られます。
【TOTO】
TOTOは、機能性を追求した結果生まれる、普遍的でミニマルな「機能美」を感じさせるデザインが多いのが特徴です。また、タンクレストイレや、タンクを壁の後ろに隠すデザインなど、空間をすっきりと見せるための選択肢も多く、空間全体のインテリア性を重視するならTOTOに軍配が上がるかもしれません。
【リクシル】
リクシルは、便器のカラーバリエーションが豊富で、シャープなフォルムから柔らかな印象のものまで、デザインの選択肢が幅広いのが魅力です。空間全体のインテリア性を重視するならリクシルに軍配が上がるかもしれません。
3.結局どっちを選ぶ?TOTOとリクシルそれぞれがおすすめな人
ここまで比較してきたように、両社にはそれぞれに魅力があります。選択に迷ったら、自分が何を一番重視するかで考えてみましょう。
【TOTO】
「きれい除菌水」をはじめとする最新の清潔機能や、長年培われたブランドの信頼性を最優先したい方。また、故障した際の補償が手厚く、将来的に部品の交換が発生した際も安心です。長く使い続けるものだからこそ、購入後のサポートを重視する方にはTOTOがおすすめです。
【リクシル】
トイレ空間をおしゃれにコーディネートしたい方や、機能と価格のバランス、コストパフォーマンスを重視したい方。
最終的には、カタログだけでなくショールームで実物を見て、触れて、ご自身の価値観に合った一台を選ぶことが、後悔しないための最善の方法です。
まとめ
トイレ選びで多くの人が比較するTOTOとリクシル。両社には、それぞれが持つ独自の強みと魅力があります。
もしどちらを選ぶか迷った場合は、業界をリードする高い技術力と、購入後も続く手厚いサポート体制を誇るTOTOを選んでおけば、まず後悔することはないでしょう。
今回の内容が、後悔のないトイレ選びの一助となれば幸いです。田口住生活設計室では、戸建て住宅、マンション、店舗・事務所などのトイレリフォームを承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.09.16
【メディア掲載】弊社代表 田口のインタビューが日刊ゲンダイDIGITALに掲載されました
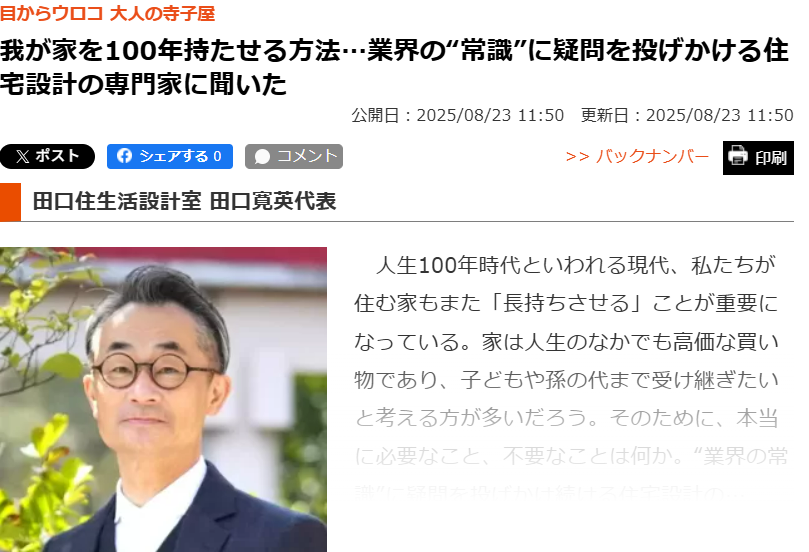
この度、弊社代表取締役である田口寛英のインタビュー記事が、2025年8月23日付の「日刊ゲンダイDIGITAL」に掲載されましたことをご報告いたします。
今回の記事では以下のようなテーマに沿って、住宅に関する情報をお話ししています。
「家の寿命は何年なのか?」
「外壁塗装は本当に10年ごとに必要なのか?」
「シロアリの被害って本当はどの程度なの?」
日頃よりご愛顧いただいているお客様、そして地域の皆様に支えられ、このような形で弊社の考え方をお伝えできる機会をいただけたことを、心より感謝申し上げます。
インタビュー記事の全文は、以下のリンクよりご覧いただけます。
▼ 掲載記事はこちら
「我が家を100年持たせる方法…業界の“常識”に疑問を投げかける住宅設計の専門家に聞いた」
日刊ゲンダイDIGITAL 掲載ページ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/376271
当社事務所に印刷したものがございますので、読んでみたいお客様がおられましたら、お立ち寄りの際に、ぜひご覧ください。
今後も、お客様一人ひとりの大切な住まいと真摯に向き合い、安心で快適な暮らしをご提供できるよう、社員一同、より一層精進してまいります。
今後とも田口住生活設計室をよろしくお願い申し上げます。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.09.13
中古住宅リフォームのポイントと注意点│リノベーションのメリットは?

自分らしい暮らしを求めて、中古住宅を購入し、好みの空間に生まれ変わらせるという選択が注目されています。新築とは一味違う、自由度の高い家づくりが実現できる一方で、購入してから「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。
理想の住まいを手に入れるためには、物件選びの段階から知っておくべき大切なポイントがいくつか存在します。今回は、中古住宅のリフォームで失敗しないためのチェックポイントについてご紹介します。
中古住宅のリフォーム前に確認すべき点
■ 新耐震基準への適合
まず何よりも先に確認したいのが、建物の耐震性です。日本では、1981年6月1日に建築基準法が大きく改正され、耐震基準が厳しくなりました。この「新耐震基準」に適合している建物であれば、一定の耐震性が確保されていると考えて差し支えありません。
一方で、それ以前の「旧耐震基準」で建てられた住宅は、大きな地震に対しての備えが不十分な可能性があります。旧耐震基準の住宅をリフォームする場合は、耐震診断や補強工事が必要になることも視野に入れておきましょう。
■ 希望のリフォームに合う構造
理想の間取りを実現できるかどうかは、建物の構造によって大きく左右されます。
例えば、柱や梁で建物を支える日本の伝統的な「木造軸組工法」は、壁を取り払って広い空間を作るなど、間取りの変更が比較的自由に行えます。しかし、壁で建物を支える「2×4(ツーバイフォー)工法」や「鉄筋コンクリート(RC)造の壁式構造」では、構造上取り除けない壁が多く、間取りの変更には大きな制約が伴います。
どのようなリフォームをしたいのか、その希望が叶えられる構造の物件かを見極めることが重要です。
■ 補助金・助成金の活用
リフォームの内容によっては、国や地方自治体が実施している補助金や助成金制度を利用できる場合があります。
対象となる工事は、耐震補強工事、断熱性能を高める省エネ改修、手すりの設置といったバリアフリー化など多岐にわたります。これらの制度をうまく活用すれば、リフォームにかかる負担を軽減できるかもしれません。
利用できる制度や条件は自治体や時期によって異なるため、リフォーム会社や自治体の担当窓口に早めに相談してみることをおすすめします。
中古住宅リノベーションのメリット
■ 新築に比べ建築費が安い
中古住宅を選ぶ大きなメリットの一つは、新築に比べて物件の購入費用を抑えやすい点にあります。その結果、節約できた分をリフォーム費用に充てることが可能です。
間取りや内装、キッチンやお風呂といった設備に至るまで、自分のこだわりを詰め込んだ、オリジナリティあふれる空間づくりを楽しみやすいと言えるでしょう。まさに、自分だけの理想の住まいを創造する喜びがあります。
■ エリアや立地の選択肢が多い
新築物件は、販売されるエリアが限定的であったり、駅から離れた郊外になったりすることが少なくありません。
その点、中古住宅はすでに市場にあるたくさんの物件の中から選べるため、希望のエリアで見つけやすいという利点があります。通勤・通学に便利な駅の近くや、住みたいと憧れていた街など、ライフスタイルに合わせて立地の選択肢が格段に広がるのは、中古住宅ならではの魅力です。
■ 資産としての価値向上
適切なリフォームやリノベーションを施すことは、物件の資産価値を高めることにも繋がります。古くなってしまった内装や設備を刷新し、現代のライフスタイルに合わせた快適な住空間にすることで、物件は新たな魅力を放ち始めます。
中古住宅購入後にリフォームする際の注意点
■ 仮住まいの必要性
リフォームの規模によっては、工事期間中にその家に住み続けることが難しくなります。特に、間取りを大きく変更したり、キッチンや浴室といった水まわり全体を工事したりする場合は、一時的に別の住まいへ移る「仮住まい」が必要です。
工事期間中の家賃はもちろん、2度の引っ越しにかかる費用や手間も考慮に入れて、全体の計画を立てる必要があります。
■ 建築基準法に抵触していないか
中古住宅の中には、現在の建築基準法に適合していない「既存不適格建築物」や、そもそも建築確認を受けずに増改築が行われた「違法建築物」が紛れていることがあります。
こうした物件は、リフォームに大きな制限がかかったり、将来建て替えができなかったりするリスクをはらんでいます。住宅ローンが利用できないケースもあるため、契約前に専門家によるチェックが不可欠です。
■ 建物の状態による工事費の高騰
中古住宅のリフォームでは、解体して初めて発覚する問題があります。壁や床を剥がしてみたら、シロアリの被害にあっていた、雨漏りで柱が腐食していた、といった隠れた劣化が見つかるケースは決して珍しくありません。
このような予期せぬ事態が発生すると、追加の補修工事が必要となり、当初の予定よりも工期が延びたり、費用がかさんだりする可能性があります。購入前に専門家による住宅診断を受けておくと、こうしたリスクを低減できます。
まとめ
中古住宅を購入してリフォームすることは、自分たちの理想の暮らしを実現するための非常に魅力的な選択肢です。
しかし、その成功は、物件を購入する前の入念な確認にかかっています。建物の耐震性や構造、法的な規制などを事前にしっかりと把握し、起こりうるリスクも理解しておくことが重要です。
専門家のアドバイスも積極的に活用しながら計画を進めることで、中古住宅のリフォームは、新築住宅を手に入れる以上の大きな満足感をもたらしてくれるでしょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.09.06
クリナップのキッチンのデメリットとは?後悔しないための事前チェックポイント

新しいキッチンを選ぶ時間は、これからの暮らしを想像するとても楽しいひとときです。しかし、高価な買い物だからこそ、「こんなはずではなかった」という後悔は避けたいですよね。
多機能で魅力的な選択肢のなかから、自分にぴったりの一台を見つけるには、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。今回は、人気のクリナップキッチンを例に、後悔しないために知っておきたい注意点と、購入前に確認すべきポイントをご紹介します。
クリナップキッチンの素材にはどんなデメリットがある?
デザインと耐久性を両立するクリナップのキッチンですが、選ぶ素材によっては知っておきたい特性があります。代表的な素材であるステンレスと人造大理石、そしてキッチンの顔となる扉材について、それぞれのメリットの裏側にある注意点を見ていきましょう。
■ ステンレスは水垢が目立ちやすい
プロの厨房のような、シャープで衛生的な印象を与えるステンレス。しかし、その美しい見た目の一方で、水滴の跡が残りやすいという側面も持ち合わせています。特に鏡面仕上げに近いタイプは、少し触れただけでも跡が気になるかもしれません。美しさを保つためには、こまめな拭き掃除が必要になります。
■ 人造大理石は高温や衝撃に弱い
温かみのある風合いとカラーバリエーションの豊富さで人気の人造大理石は、デザイン性を重視する方に特に支持されています。その一方で、ステンレスに比べると熱や衝撃にデリケートな素材です。熱い鍋を直接置くと変色や変質の原因になりますし、硬く重いものを落とせば、キズが付いたり最悪の場合は割れてしまったりする可能性もゼロではありません。
■ 扉材によっては色あせやキズが気になる
キッチンの印象を大きく左右する扉材も、慎重に選びたいポイントです。クリナップのキッチンには様々なグレードの扉材が用意されていますが、種類によっては経年で色があせたり、日々の使用で細かなキズが付きやすかったりするものもあります。特に、日当たりの良い場所にキッチンを設置する場合、紫外線による影響も考慮に入れておくと、長く満足できる選択につながるでしょう。
クリナップのキッチンを選ぶ際のポイント
日々の調理をスムーズにするには、収納力や作業動線などの使い勝手が鍵となります。カタログに掲載されたスペックだけでは見えにくい、実際に使ってみて気づくポイントを紹介します。
■ 引き出しのサイズ(深さや奥行)をチェックする
大容量で使いやすいと評判のクリナップの収納ですが、しまう物との相性によっては不便を感じるケースもあるようです。特に「引き出しの高さが思ったよりなく、背の高い調味料ボトルや愛用の鍋を立てて収納できない」といった声が聞かれます。普段使っている調理器具やストック品のサイズを確認し、収納スペースにきちんと収まるかシミュレーションすることが大切です。
■ キッチンの高さと導線をチェックする
キッチンのワークトップの高さは、毎日の調理の快適さを左右します。低すぎても高すぎても作業効率は落ちてしまいます。使う人の身長に合っていないと、無理な姿勢が続いて腰痛の原因になることもあるため、ショールームでシミュレーションしてみることがおすすめです。
また、一人で黙々と料理に集中したいのか、家族や友人と会話を楽しみながら使いたいのかによっても、最適なレイアウトは変わります。将来の家族構成の変化も見据えながら、ご自身の調理スタイルに本当に合った機能かどうかを見極めましょう。
■ ごみ箱の設置場所をイメージしておく
デザイン性の高いキッチンで意外と見落としがちなのが、ごみ箱の置き場所です。調理中に出る生ごみから分別が必要な資源ごみまで、すっきりと収めるスペースを設計段階で考えておかないと、後から置き場所に困りかねません。必要なごみ箱の数やサイズをあらかじめ想定し、キャビネットの一部をごみ箱スペースとしてプランニングするなどの工夫が必要です。
購入前に確認すべきポイントは?
ここまでの注意点を踏まえ、最終的に後悔のない選択をするために欠かせない、購入決定前の最終チェックポイントをまとめました。理想のキッチンを実現するために、ぜひ押さえておきたい視点です。
■ 実物をショールームで体感するのが確実
カタログやウェブサイトの情報だけでは、素材の本当の質感や色味、引き出しを開閉する際の滑らかさといった感覚までは分かりません。購入を決める前には、ぜひ一度ショールームへ足を運び、実物に触れてみるべきです。実際にキッチンに立って高さを確かめたり、収納の使い勝手を試したりすることで、図面だけでは気づかなかった発見が必ずあるはずです。
■ 長期的なメンテナンスの手間も考慮すべき
キッチンは、一度設置すれば10年、20年と長く付き合っていく大切な設備です。導入時の価格だけでなく、日々の掃除のしやすさや、美しさを保つためにどれくらいの手間がかかるかといった、長期的なメンテナンスの視点も忘れてはなりません。素材ごとの手入れ方法を事前に把握し、ご自身のライフスタイルに合っているかを考えてみましょう。
まとめ
クリナップのキッチンを選ぶ際には、デザインの魅力だけでなく、知っておきたい注意点も存在します。ステンレスや人造大理石といった素材ごとの特性や、収納の寸法、ワークトップの高さといった使い勝手の側面を事前に理解しておくことが、後悔しないための第一歩です。
そして何より、ご自身の調理スタイルやライフプランとキッチンを照らし合わせることが不可欠です。最終的には必ずショールームで実物を体感し、長期的な視点を持って、ご自身にとって最高のパートナーとなる一台を選んでください。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2025.08.31
屋根の遮熱対策とは?暑い夏を快適に過ごせる住まいにしよう
夏の二階の、あのむっとするような暑さ。
エアコンを何度に設定しても、なかなか涼しくならないと感じたことはありませんか。
その不快な暑さの原因は、もしかすると屋根にあるのかもしれません。
屋根は家の中で最も太陽光を浴びる場所であり、その熱が直接室温の上昇につながっているのです。
しかし、適切な対策を施すことで、その熱を大幅に和らげることが可能です。
この記事では、屋根の遮熱対策にはどのような方法があるのか、それぞれの特徴と選び方のポイントをご紹介します。
屋根における遮熱対策の主な方法は?
・最も手軽で一般的な「遮熱塗料」
屋根の遮熱対策として、現在最も広く普及しているのが「遮熱塗料」を塗る方法です。
これは、太陽光に含まれる熱の原因となる赤外線を効率よく反射する特殊な顔料を含んだ塗料のこと。
既存の屋根の上から塗装するだけで、屋根の表面温度が上昇するのを抑え、結果として室内へ伝わる熱を軽減させる効果があります。
比較的シンプルな工事で済むため、コストを抑えつつ遮熱対策を始めたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。
・塗料と併用して効果を高める「遮熱シート」
次にご紹介するのが、屋根の下地部分に施工する「遮熱シート」です。
これは、屋根材の下にある野地板という板の上に敷くシート状の建材で、輻射熱を反射する働きがあります。
遮熱塗料が屋根の表面で太陽光を跳ね返すのに対し、遮熱シートは屋根材を通過してしまった熱が屋根裏へ侵入するのを防ぐという役割を担います。
この二つを併用することで、より強力な遮熱効果を発揮させることが可能です。
・断熱効果も期待できる「屋根カバー工法」
屋根カバー工法は、今ある屋根材の上から新しい屋根材を重ねて葺くリフォーム方法です。
この工法で遮熱性能や断熱性能を持つ屋根材を選べば、高い遮熱効果が期待できます。
屋根が二重構造になることで空気の層が生まれ、熱が伝わりにくくなるため、夏は涼しく、冬は暖かいという断熱効果も向上します。
屋根材自体の劣化が進んでおり、メンテナンスも兼ねて根本的な対策をしたい場合に有効な方法です。
遮熱塗料の効果を最大限に引き出すポイント
・色選びで変わる太陽光の反射率
遮熱塗料の効果は、実は塗料の色によって大きく変わるという事実があります。
一般的に、白やベージュといった明るい色ほど太陽光を反射しやすく、黒や濃いグレーなどの暗い色は光を吸収しやすいため、遮熱効果は低くなります。
塗料メーカーのカタログには「日射反射率」という数値が記載されているので、デザイン性だけでなく、この数値を参考に色を選ぶことが効果を実感するための重要な鍵となります。
・塗料の性能を左右する耐用年数と機能性
遮熱塗料には、シリコン、フッ素、無機といった様々なグレードが存在し、それぞれ遮熱性能の持続期間、つまり耐用年数が異なります。
価格が安いという理由だけで選ぶと、数年で効果が薄れてしまい、結果的に再塗装のコストがかさむことも。
長期的な視点で、自宅の環境や予算に合った塗料を選ぶことが大切です。
また、汚れが付着しにくい低汚染機能を持つ塗料は、反射率の低下を防ぎ、長く性能を維持する助けになります。
・適切な施工ができる業者選びの重要性
どんなに高性能な塗料を選んだとしても、それを塗る職人の技術や知識が不足していれば、本来の効果は発揮されません。
例えば、塗装前の高圧洗浄や下地処理が不十分であったり、メーカーが定めた塗料の量や乾燥時間を守らなかったりすると、早期の塗膜の剥がれや性能低下につながります。
業者を選ぶ際は、価格だけで判断せず、施工実績や保証内容をしっかりと確認し、信頼できる専門業者に依頼することが何よりも重要です。
どの遮熱対策を選ぶべき?費用と状況別の比較
・コストを最優先するなら「遮熱塗料」
まずは費用を抑えて対策を始めたい、という方には「遮熱塗料」による塗装が最も現実的です。
屋根の状態が比較的良好であれば、塗装だけで十分な効果を得られます。
遮熱効果を長持ちさせるためにも、塗料は吟味して選びましょう。
また、外壁の塗装も検討している場合は、同時に工事を行うことで足場の設置費用を一度で済ませることができ、トータルコストを大きく削減できるというメリットも見逃せません。
・屋根の劣化が進んでいるなら「屋根カバー工法」
屋根材にひび割れやサビ、色あせが目立つなど、劣化が進行している場合は、塗装だけでは根本的な解決にならないことがあります。
そうした状況では、屋根の補修と遮熱対策を同時に行える「屋根カバー工法」が適しています。
初期費用は塗装よりも高くなりますが、家の寿命を延ばし、長期的な安心感を得られる有効な投資となるでしょう。
・長期的な効果と快適性を求めるなら複合的な対策
最高の快適性を追求したい、あるいは長期的な視点で光熱費を削減したいと考えるなら、一つの方法に絞るのではなく、複数の対策を組み合わせるのが最も効果的です。
例えば、屋根カバー工法で断熱性の高い屋根材を選び、その上に遮熱塗料を塗る、あるいは遮熱塗料と遮熱シートを併用するといった方法です。
初期投資はかさみますが、それに見合うだけの快適性と経済的なメリットを将来にわたって享受できるはずです。
まとめ
夏の厳しい暑さを和らげるためには、屋根の遮熱対策が非常に有効です。
主な方法として、手軽な「遮熱塗料」、より効果を高める「遮熱シート」、そして抜本的な解決策となる「屋根カバー工法」があります。
また、遮熱塗料を選ぶ際は、効果を左右する色や塗料のグレード、そして施工業者の技術力が重要なポイントになります。
ご自宅の屋根の状態や予算、そしてどれくらいの効果を求めるのかを総合的に考え、最適な方法を選ぶことが、快適な住まいへの第一歩となるでしょう。
屋根の遮熱対策をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30年以上の現場経験を持つ建築士とスタッフが、お客様の人生を考えて住まいをつくる会社です
【全国対応可能】調査/コンサルティング
劣化度の調査、耐震診断、耐震補強、床下調査
【埼玉県/関東全域出張可能】工事
修繕、リフォーム、リノベーション、外壁塗装工事、介護リフォーム
キッチン・浴室・トイレ改修、内装工事、間仕切り工事 等
お気軽にご連絡ください♪
電話:048-729-4517
〒331-0802 さいたま市北区本郷町1579
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::